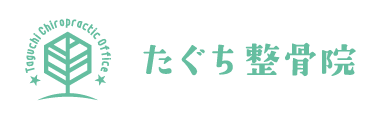
 院長:田口
院長:田口お気軽にご相談ください!
こんにちは、たぐち整骨院の田口です。赤ちゃんの頭の形について、不安を感じているお母さん、お父さんからのご相談が本当に増えています。生後2ヶ月の健診で後頭部が少し平らになっていることに気づいたとき、「絶壁になったらどうしよう」と心配になる気持ち、とてもよくわかります。実は赤ちゃんの頭の形の変形を防ぐためには、やってはいけないことを正しく理解しておくことが何より大切なのです。
当院では開院以来、数多くの赤ちゃんの頭の形でお悩みの保護者の方と向き合ってきました。その中で気づいたのは、皆さんそれぞれ一生懸命、多くの方が善意で行っている対策が、実は逆効果になっているケースが少なくないということです。今回は正しい知識を持って対応していただけるよう、絶対に避けるべき習慣と本当に効果的な方法についてお話しします。


もっと早く知りたかった~をなくしたい。そう願って書きました。


赤ちゃんの頭蓋骨は大人と違って非常に柔らかく、外からの圧力で簡単に形が変わってしまいます。これは脳の成長に合わせて頭蓋骨が柔軟に大きくなれるようにという自然の仕組みです。ただし、同時に長時間同じ方向からの圧迫を受け続けると変形してしまうリスクも抱えています。海外では仰向け寝推奨キャンペーン以降、頭の形の変形の発生率が約47%まで増加しているという報告もあります。
頭の形の変形には主に斜頭症、短頭症、長頭症の3つのタイプがあります。斜頭症は頭が左右非対称になる状態で、短頭症は後頭部が平らになる絶壁頭のことです。これらは病気ではありませんが、放置すると1歳半から2歳頃に頭蓋骨が固まってしまい、その形のまま成長してしまうのです。
当院に来院される保護者の方の多くが、知らず知らずのうちに間違った対策をされていることがあります。特に深刻なのが、正しい情報を誤解してしまっているケースです。
乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクから、うつ伏せ寝は絶対に避けるべきとされています。これは医学的に正しい情報です。ところが、この情報が「うつ伏せ自体がいけない」という認識になってしまっているケースが非常に多いのです。新生児の段階から「一切うつ伏せにしてはいけない」と思い込み、ずっと仰向けで寝かせ続けた結果、向き癖から斜頭症や短頭症を発症してしまうことがあります。
大切なのは、寝ているときのうつ伏せ寝は危険だが、起きているときの保護者の監視下でのうつ伏せ遊び(タミータイム)は推奨されるということです。タミータイムは頭への圧迫を減らすだけでなく、首や肩、背中の筋肉を鍛える効果があります。生後1ヶ月頃から、赤ちゃんが起きているときに数分からでも取り入れることで、頭の形の変形予防に大きな効果があるのです。
向き癖がいけないとわかると、多くの保護者の方が「逆向きばかりに向かせよう」と頑張られます。右ばかり向いているから左向きに矯正しよう、という発想自体は間違っていません。しかし、無理に逆向きばかりに向かせ続けることで、首や背中の緊張が強まり、かえって向き癖が強くなってしまうケースが少なくありません。
赤ちゃんの身体は繊細で、無理な姿勢を強いると筋肉が緊張してしまいます。その結果、元々向いていた方向へ戻ろうとする力がさらに強くなり、向き癖の改善どころか悪化させてしまうのです。大切なのは無理に矯正するのではなく、赤ちゃんが自然と両方向を向けるような環境を整えることです。
これまでの臨床経験から、特に注意していただきたい習慣をまとめました。これらは赤ちゃんの頭の形や身体の発達に大きな影響を与えます。
赤ちゃんには向き癖があることが多く、気づけばいつも同じ方向を向いて寝ています。これが最も多い頭の形変形の原因です。同じ部分ばかりが圧迫されることで、その部分が平らになったり左右非対称になったりします。授乳の向きや寝かせる位置を意識的に変えること、おもちゃや声かけの位置を工夫することで、自然と両方向を向ける環境を作ることができます。
ドーナツ枕は頭の形を整えるために良いと思われがちですが、実は医学的な効果は証明されていません。それどころか、枕の使用は乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクを高める可能性があるため、日本小児科学会でも生後12ヶ月までは枕の使用を推奨していないのです。頭の形が心配だからとドーナツ枕を使うことは、別のリスクを招くことになりかねません。
バウンサーや授乳クッション、チャイルドシートに長時間寝かせ続けることも避けるべき習慣です。これらの育児用品は便利ですが、同じ姿勢が続くことで頭の特定部分に圧力がかかり続けてしまいます。起きているときはできるだけ抱っこしたり、姿勢を変えてあげたりすることが大切です。特に首が座ってきたら縦抱きも積極的に取り入れましょう。
SIDS予防のために仰向け寝が推奨されているのは事実ですが、起きているときまで仰向けにこだわる必要はありません。むしろ、起きているときは保護者の監視下でうつ伏せ遊びをさせることが、頭の形の変形予防にも身体の発達にも重要です。寝るときは仰向け、起きているときは様々な姿勢を経験させるというメリハリが大切なのです。
「様子を見ましょう」と言われて何もしないことが、実は最も避けるべき習慣かもしれません。確かに軽度の変形は自然に改善することもありますが、中等度以上の変形は自然改善が期待できないケースが多いのです。生後7ヶ月を過ぎると改善変化が少なくなるため、早期の専門的な評価と対応が重要になります。
やってはいけないことを知ったら、次は正しい対策を実践していきましょう。赤ちゃんの頭の形は適切なケアで改善が期待できます。
無理に向きを固定するのではなく、赤ちゃんが自然と両方向を向きたくなる環境を作ります。抱っこの仕方を工夫する、ベビーベッドの位置を変える、おもちゃの位置を工夫する、話しかける位置を意識するなど、日常の中でできることがたくさんあります。赤ちゃんは興味のある方向を向く習性があるので、その特性を活かすのです。
生後1ヶ月頃から、赤ちゃんが起きていて機嫌の良いときに、保護者の目の届く範囲でうつ伏せの時間を作ります。最初は1日1〜2分から始めて、赤ちゃんの様子を見ながら徐々に時間を延ばしていきましょう。これは頭への圧迫を減らすだけでなく、首や肩、背中の筋肉を鍛える効果もあります。生後3〜4ヶ月頃には1日に合計30分~40分程度(1回の時間は赤ちゃんが楽しめる程度)を目標にすると良いでしょう。
授乳のたびに左右を交互にする、抱っこの向きを変えるなど、日常のケアの中で意識的に変化をつけていきます。特に縦抱きは頭への圧迫が少なく、首が座ってきたら積極的に取り入れたい方法です。起きているときはできるだけ抱っこしてあげることで、頭への圧迫時間を減らすことができます。
家庭でのケアも大切ですが、専門家の判断を仰ぐべきタイミングもあります。以下のような場合は早めに相談することをおすすめします。
当院では国家資格を持つ院長が、検査から施術まで責任を持って担当しています。赤ちゃんの繊細な身体に対して、豊富な経験と確かな技術で5gタッチといわれる安全かつ効果的な施術を提供しています。ご相談はできるだけ早い方が安心です。生後1か月から赤ちゃん整体は可能です。一人ひとりに合わせた最適な施術プランをご提案します。
向き癖の原因として見逃せないのが筋性斜頸です。これは首の筋肉(胸鎖乳突筋)が緊張して硬くなり、首が一方向に傾いてしまう状態のことです。この場合、単に環境を整えるだけでは改善が難しく、専門的な評価と施術が必要になります。
筋性斜頸があると、赤ちゃんは物理的に特定の方向しか向けなくなります。無理に逆向きに向かせようとすると、緊張している筋肉がさらに硬くなり、悪循環に陥ってしまうのです。当院では、このような筋肉の緊張を優しく緩めていく施術も行っています。
頭の形の矯正方法として、ヘルメット治療という選択肢もあります。これはオーダーメイドのヘルメットを1日23時間、約6ヶ月間装着する形状誘導療法です。効果的な治療法ですが、いくつか知っておくべきポイントがあります。
まずヘルメット治療は自費診療で約45万円から60万円程度の費用がかかります。また開始時期が生後3ヶ月から7ヶ月までと限定されており、このタイミングを逃すと効果が期待できなくなります。赤ちゃんへの負担や汗疹などの副作用も懸念されるため、専門医としっかり相談して判断することが大切です。当院では、ヘルメットを使わない自然な方法で可能な限り改善を図りたい方のサポートも行っています。
赤ちゃんの頭の形は、単に見た目の問題だけではありません。重度の左右差がある場合は、将来的に運動能力や噛み合わせ、聴力に影響する可能性も指摘されています。また、見た目のコンプレックスから心理的な影響を受けることもあり、お子さまの自信や社会性にも関わってくる大切な問題なのです。
頭蓋骨が柔らかい時期は限られています。生後7ヶ月を過ぎると改善変化が少なくなり、1歳半から2歳頃には頭蓋骨が固まってしまいます。だからこそ、早めの正しい対応が何より重要なのです。ただし、焦って無理な矯正をすることは逆効果になります。赤ちゃんの身体の状態を正しく理解し、適切な方法で対応することが大切です。
私自身も学生時代に適切な治療を受けられず後悔した経験があります。原因を追求することなく、その場しのぎの治療を続けても決して良くなることはありません。だからこそ、お子さまの将来のために、今できることを精一杯サポートしたいと考えています。赤ちゃんの頭の形でお悩みなら、一人で抱え込まずにいつでもご相談ください。当院では検査によって現在の状態を正確に把握し、赤ちゃんの身体に負担をかけない方法で最善のアプローチを一緒に考えていきます。お子さまの健やかな成長のために、私たちにできることがあります。

